日本におけるスイスについての報道でよく見るのが安楽死、自殺ほう助についてではないかしら。現在合法化されているのはベルギー、オランダとスイス。それにイギリスでは審議中でしたっけ?
しかし、日本の皆様が思うほどはスイスでの安楽死/自殺ほう助は簡単ではない。第一の関門は「家族の反対」。
知人のお母さんは第二次世界大戦後にオーストリアからスイスに渡り、数々の苦労の中、働きに働いてきた人。元気で頑固。退職後は鉄道・バスの年間乗り放題パスを手に、遠出した先でお茶を飲んで帰ってくるのを日常にしていた。コロナ禍でも家にはとどまらず、家族が止めても決して言うことを聞かずに鼻マスク、ワクチン拒否でガラガラの電車で出かけ、自動販売機の釣銭口に小銭が残っていないかを触って確認するのが趣味だった!そんな気ままな一人暮らしを楽しんでいた彼女が80代後半でひどい腰痛で歩くのも苦痛、出かけるのが困難になると、自殺ほう助団体に申し込んだ。そのことを子供に告げたところ、子供たちは猛反対。医療機関にツテがあった息子は八方手を尽くし、名医の予約を取り付け、渋る母親を説き伏せて手術を受けさせた。手術と長い療養でも痛みが完全に取れることは無く、術後は近い範囲での移動にとどまったけど、痛い痛いと言いながらもそれでも最後まで頑固に一人暮らしを貫いて、最後は1週間ほど入院して亡くなった。
10年位前に報道された件だが、一人暮らしの超高齢者が、連れ合いや親しい友人もいなくなったから、と自殺ほう助で人生を終わらせることに決め、そのことを兄弟たちに告げたところ、兄弟らがそれを阻止しようと司法に訴えた。司法判断で自殺ほう助は阻止されたが、その高齢者は自殺。本来は家族に看取られて平穏に(?)死ぬするつもりだったのが、銃での自殺という結末になった。
老人ホームで暮らす90代後半の知り合いの母親は、死にたいので幇助団体に申し込んで欲しいと娘に頼んだ。子供たちや近所の人が頻繁に面会に来るし、ホームでの食事も美味しい。広い個室を占有、何の不自由もないし、あんなに尽くしている娘を悲しませるなんて、と息子の方は悲しむというより怒った。大層怒ったが、それでも某自殺ほう助団体のサイトを調べたところ「申し込んでから最短でも90日」とあった。悲しみながらも団体に電話したところ、それはそれは冷たい口調で「家が燃えてから火災保険に入っても遅いでしょう?現在安楽死希望が1000人以上いて順番待ちなのです」と暗に断られたそうだ。もっとも、ようこそいらっしゃいませ!の口調で応対されてもどうかと思うけど、スイス人もびっくりの塩対応だったらしい。自殺ほう助団体への登録申請は早めに、多少応対がヨーロッパ式でも(悪くても)めげずに「私はどうしても死にたいんじゃ!」と強固に粘ることが必要らしい。
たとえ申請したとしても、その後は複数の医師との面談をクリアしなければならない。希望者の状況や精神状態を鑑定し、本人の意思を確認し、一時の気の迷いや周囲から強制されたものではないことなどが確認できて初めてプロセスが進むとか。死にたくなったとしても、決して簡単に死ねるわけではない。
死にたがっていた90代後半の御婦人は幸いにも掛かり付け医との面談で大分落ち着き、自殺ほう助団体に頼るという考えはおさまり、子供らは安堵!身内にとっては、何の不自由もないし寂しくならないように気を尽くしているのに何が不満なの?と思いたくなるが、でも、彼らの誰も90代後半になったことないのだ。彼女の気持ちは60代の誰にも分からない。
以前、完全バリアフリーの豪邸に住む見た目元気な90代の方が、それでも「毎日、一足ごとに、転ばないようにと注意しながら歩くのはうんざりなの!もう嫌なのよ!」とおっしゃっていたのを思い出す。
新聞の死亡告知欄には時折、割と若い年齢なので難病だったのかなあ、と思う方が、病院関係者などへと共に、自殺ほう助団体への感謝の一言が添えられていることがある。
さて「自殺」というのはキリスト教的には大変な罪になるそうで、例えば画家のゴッホは自殺だったため、教会での葬儀を拒否されて仕方なく下宿先で葬儀となったわけだ。現在の教会ではそれは許されているようで、例えばこの10年間で私が報道で知った、大聖堂で行われた葬儀、それぞれローザンヌとフリブールの大聖堂での2件だが、2件とも超大物が自殺で亡くなっての葬儀だった。超大物となると参列者の都合で大聖堂での葬儀となるのね。

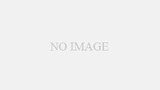

コメント